
 |
||
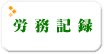 |
||
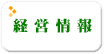 |
||
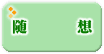 |
||
 |
||
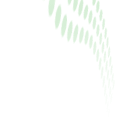 |
||

|
||||||
| □2003.12.04 (Thu) | ||
| ■ピアノ発表会 秋の終わりの日曜日。 朝、翼小学校で小学二年生と三年生の息子たちの学芸会が行なわれ、続いて昼からは、同じく二人のピアノの発表会があった。 ピアノのリハーサルは午前中から行なわれていたが、翼小学校の児童だけは学芸会が終了するやいなや、発表会場である「かわら美術館」へ駆けつけ、リハーサルをすませてからすばやく昼食をとり、本番へ臨んだのだった。 朝からの過密スケジュールのせいか、緊張の糸が少しほぐれ、それが息子たちには幸いしたとみえて、本番では練習どおりの発表ができた。 逆に時間をもてあましていれば、あれこれ考えて、練習どおりの成果は出なかったかもしれない。時間がありすぎるのは衛生上良くないのである。 いずれにしても、練習のときの“でき”以上のものは、本番では出にくい。 練習のときの“でき”がどうにかこうにか出せれば一人前で、たいがいはそれ以下に落ち着く。 息子たちもそうで、一人はどちらかというと几帳面だから、練習の際でも間違えることなく人並みにこなしていくが、もう一人はずぼらで、練習でも最後まで間違えっぱなしだった。 それが本番に出ただけである。 ずぼらな方は、発表会の少し前まで楽譜なしではピアノが弾けず、先生に「生徒の中で、楽譜を見なければ弾けないのは、おばあさんとあなただけよ」と言われていた。 それで発奮したのか、発表会では楽譜を見ずに弾けた。 「おばあさん」はやはり楽譜を見て弾いていた。 さて、先生の言葉の中に登場した「おばあさん」。息子たちの話では、七十三才と七十七才の二説あって、どちらが本当かわからない。 しっかりした白髪の中に、上品さと気骨とをため込んだ「半生」がうかがわれるが、子供たちに混じって、発表会に参加するのは並みの根性じゃない。 孫のような子供たちの中で、あるいは恥ずかしい思いをするかもしれない発表会場の、ピアノの前に座ることへの恐怖感。 七十才を過ぎてピアノを習い始め、自分の覚えの悪さに泣いた夜もあっただろう。 年齢から推察して、青春時代は「戦争」のさなかにあったはずだ。 女性として一番美しい時代が「戦争」の真中で、ピアノを学びたくても学べず、ピアノを弾きたくても弾けない時代だったのだ。 それを当たり前と受け止め、戦争という非日常の世界で、歯を食いしばって生きてきたのだろう。 ピアノを学ぶこともピアノを弾くことも、「夢」だったに違いない。 それから半世紀が過ぎたある日、青春時代の「夢」のかけらをつかもうと、ピアノを習い始めたのではなかったか。 そんな気がする。 「おばあさん」が演奏した『ふるさと』と『バラが咲いた』は、時々曲が立ち止まったり、脱線したりしたが、ゆっくりと丁寧に弾き終えた。 ピアノの椅子から立ち上がり、舞台の前方へ歩を進め、観客にお辞儀をするやいなや、喝采の拍手が出迎えた。 「おばあさん」は子供のように少しはにかんでいた。 友人であろう老人が「おばあさん」に花束を手渡し、両手を握りしめた。 そして互いに涙ぐんだところで、また喝采が起きた。 今日、息子たちの母親が撮った写真が出来上がってきた。 記念写真の中には、息子たちの顔も「おばあさん」の顔も晴れやかに写っている。 一つの仕事をやりとげた安堵感と達成感が横溢している。 二年に一度のピアノの発表会。 次の発表会にまた「おばあさん」は参加するだろうか。 わたしはふと、そんなことを考えていた。 |
||
| □2003.11.15 (Sat) | ||
| ■川柳七句 すり切れた靴が歩行を覚えてる 靴底の捨てられぬ過去が歩き出す リュックサック明日への歩み詰めておく 歩いたり走ったり午後がたそがれる 流れ雲ともに歩いた夕焼けた 歩道橋空の青さも罪になる 何か足らず平均台を歩いてる |
||
| □2003.11.03 (Mon) | ||
| ■晩秋 早いもので晩秋に入っていきます。 11月の景色は、入日の赤さがやけにさびしくて、人恋しくなっていく・・・はずなのですが、今年はあまりに暖かく、人にすがることなく自分で生きていけそうです。 冷茶を飲んで、カーテン越しの日差しをいっぱいに浴びて、まだまた紅葉には早い木々を遠くから眺めています。 日常の足が速く感じられるのは、私の足が遅くなったせいでしょうか。 様々なしがらみに足をとられ、ほんの小さな距離を行き来しているだけの生活なのでしょうか。 しかし、それは幸せな暮らしの中でのほんの一瞬の「迷い」て゜あって、贅沢なことなのでしょう。 何かが足りないと思うくらいが、日常においてはちょうどいいことかもしれません。 腹八分目をわきまえ、小さな幸せを享受できればいいのです。 湯山公園で子供たちとドッジボールやサッカーをして遊びます。 勢いが強くなってきた球を受けて、子供たちの成長を知ります。 近くで見ると木々の葉か゜ほのかに赤みを帯びてきています。 何気ない日常の中の色々な発見。 振り返れば、底抜けに明るい日差し。 晩秋の空の青さは罪ではないですか。 |
||
| □2003.10.24 (Fri) | ||
| ■「いい人」をやめると楽になる 曽野綾子さんの『「いい人」をやめると楽になる』は、心の疲れを知る人にはなかなかの名著です。 「心の疲れ」と書きましたが、生きていれば、多かれ少なかれそれは誰にでもあります。 曽野さんはこんなふうに言っています。 「いい人をやめたのはかなり前からだ。 理由は単純で、いい人をやっていると疲れることを知っていたからである。 それに対して、悪い人だという評判は、容易にくつがえらないから安定がいい。 いい人はちょっとそうでない面を見せるだけですぐ批判され、評価が変わり、棄てられるからかわいそうだ」 「日本では生きるということは、選択を伴ったものである。 しかし、私は途上国を歩いているうちに、生きることには選択もできない場合が多いことを知った。 夕食に食べるものがなければ、人はどうするか。 盗むか、乞食をするほかはないのである。 どちらもあまりいいことではない。 しかし、乞食をすることも盗みをすることも悪いとなると、国中貧しくて産業はなく、飢饉に襲われた土地ではどうして生きて行ったらいいのだ。 多くの土地では、いい人として生きることなどやめて、できることをして生きて行くほかはないのだ」 3年ほど前、浄土真宗の門徒さんが中心になって催されている「心の元気塾」に出席しました。 そのとき講師を勤められていた中村薫さんが、こんなことを言っていたのを思い出します。 「常日頃冷静でまじめな人は、戦争に対してもまじめである」 ああそうか、いい加減でいいんだ、と思いました。 いいかげんではなく、いい加減。 このあたりが生きていく上において難しい。 |
||
| □2003.10.13 (Mon) | ||
| ■川柳七句 底冷えにエンゲル係数上がり切り 寝て一畳起きて半畳の寒さよ トビウオに浮揚の術を学ぶ夏 江戸っ子を気取ってさびし持ち合わせ 船頭の川下る夕逆光線 舟遊びススキの光がこぼれる日 秋蝶が棹につかまり川下り |
||
| □2003.09.30 (Tue) | ||
| ■夏の終わり 暦の上ではずっと前に夏は終わっていますが、なぜだか今日が夏の終わりのような気がします。 立秋が8月なのは、旧暦とかが存在して、理屈ではわかっていても、この肌が理解できないのです。 秋はやはり、肌が多分に寒さを感じるときであって、10月の声を聞かなければそれは無理というものです。 その意味では明日からが秋の始まりといえそうです。 この夏の心のアルバムをひもといてみて、何があったて゜しょうか。 花火、西瓜、かき氷、噴水、向日葵、朝顔・・・夏の風物詩には出会いましたが、肝心の海が抜け落ちてしまっています。 夏は海が命です。 地平線の彼方に積乱雲が涌き出し、何かの始まりを予感できなければ、どうして夏といえるでしょうか。 沖合いをさっそうとトビウオが飛行し、果てのない旅路の向こうから、また明日が始まるのです。 貝殻を捜すように、もう一度夏を捜しに海へ行きたい。 遅い夏を少しだけでも取り戻せればいいと、そんなことを思いながら、また日が暮れていきます。 |
||
| □2003.09.15 (Mon) | ||
| ■百日紅 傘を差しても差さなくても 不自然でない日は 「あいにく」 という言葉が、むしろ自然でなく 百日の歩みを、雨のようにこの町に刻む。 草花が欲するほどよい濡れが 水絵の具を溶く水のように、わたしにはかけがえのないものだ。 青草も延びほうだい延びた。 どれもがまっすぐ延びている。 なかには可憐な花をつけている、名前も知らぬ わたしの胸のよりどころとなるだけの たかだか百日の生を天に向けている青草 わたしがよりどころとするのであれば 「あいにく」であるか。 ちりぢりの淡い紅をひいて 青草の間合いに隠れるように しかし確かに目を射る百日紅 どこでどう間違ったのか けだるそうに咲く普段の面持を捨て 哲学的な顔して咲く百日紅 短命を悟ったのか、朱に交わったのか わずかな雨に濡れた樹皮がいよいよ滑りやすく 猿の遊戯をさらに遠ざけるが・・・・ 百日過ぎれば、この町を後にする。 傘を差しても、差さなくても ほどよく濡れた薄衣に まっすぐ伸ばした手を いくらでも振ることができる。 |
||
| □2003.09.07 (San) | ||
| ■この夏は寒かった 温暖化が叫ばれてから久しく、近年はいずれも暑い夏でしたが、ことしはちょっと趣が違います。 「冷夏で喜ぶのはパン屋さん」という貧困な連想は少し恥ずかしい気がしますが、元「敷島製パン」社員の身の上ですと、パンの消費に目がいってしまうのです。 確かに、冷夏ですとパンの消費は5%くらい上がります。 逆に冷麦、素麺の類やアイスキャンデー、飲料水の消費は同じくらいの割合で落ちていきます。 今頃、「敷島製パン」の社員は臨時賞与の胸算用をしていることでしょう。 どこまでいっても話が俗物的でいけません。 宮澤賢治のように「寒さの夏はおろおろ歩き・・・」という発想がないものでしょうか。 自分にあきれてしまいます。 さて、寒かった夏も暦の上では過ぎ去り、初秋となっていきます。 夏の寒さにうって変わり、9月に入ってからの暑さはどうでしょう。 夏を出し惜しみした季節が、ここでにわかにバランスをとって1年の終盤になだれ込もうとしています。 どんな秋がくるでしょうか。 そして、どんな出会いがあるでしょうか。 |
||
| □2003.08.28 (Thu) | ||
| ■水物だからね・・・ 息子を乗せて、近くのハンバーガーショップヘ行く。 車中、「こんな雨の日にもお客さん来るのかな」と息子。 「満員だよ。みんなどこへも行けないから、マクドナルドが流行るのさ」と私。 何のことはない、駐車場では雨水が白線を洗っている。 息子が心配したとおり、店内には数組のお客だけ。 まさか町中が布団を被って長雨の止むのを待っているのでもあるまいし。 梅雨も終わりに近づいた。もうすぐ蝉の初時雨があるだろう。 始まりが走り梅雨なら、終いを何と言うのだろうか。 入梅はその日のうちに宣言されるが、梅雨が明けたことがわかるのはずっと後なので、言い当てる言葉がないのだろうか。 今年は雨がよく降った。それも強い雨が多かった。仕事上の大事な書類を滴らし、あわててハンカチで拭いたり、突然の雨に軒下に飛び込んだり。 傘を持たずに家を飛び出しては、濡れ鼠となる日々。 間の悪さときたら一人前で、それを棚に上げて「端から降れよ」と雨を睨んだりした。 若さが取り柄のうちは雨に滴れるのもいい。滝のように打たれるのもいい。 ずぶ滴れの衣服を脱ぐと体から水蒸気が立ち昇り、ほどよい熱をあたりへ放っていく。 そんな眺めはいい。 仕事や家庭のある身となっては、せいぜい水槽の中をメダカのように泳ぐだけだ。 行き場がないから、こうして息子と向き合ってハンバーガーを食べ、ポテトを噛り、コーラを飲んでいる。 人は雨の日を“あいにく”と言って嫌う。 それは傘や長靴を用意するのが面倒なだけでなく、雨が景色を曇らせていくからだろうと思う。 黒やグレーの色が景色に混ざっていって存在をぼかしてしまう。 個性をなくしたものにひどく魅力が失せるように、何もかもが自分の絵の具を箱に仕舞い込み、引きこもってしまう。これでは行き場をなくした私と同じだ。 少し小降りになってきたのを幸いに、息子は店の向かい側にある公園へと私を誘う。 いつもの週末とは違って家族連れの賑わいはなく、私たち父子だけがここにいる。 二本の傘がしばらく歩く。隣家の人が植樹した白樺が、幹をだいぶ天空へ延ばしている。 “飛翔”と彫られた乙女の像が淋しげに宙を躍動している。 やがて息子は、水が潤う芝の上を一方へ駆け出していく。 傘を捨てて、時には雨に濡れてみるのもいいか。 長い長いローラー滑り台を、息子と一緒にびしょ濡れになって滑るのもいいか。 ツリー状のジャングルジムの上で踊るのも、高処から網を掴んで、ターザンのように風を切ってみせるのも・・・。 “飛翔”できない父にとって、息子はいつも遠い存在だ。 遥か彼方のコバルトの海を、まるで熱帯魚のように泳いでいる。 水槽の中のメダカが、水槽から飛び出し沖合へ出ていくのにどれだけの時間がかかることか。 ややもすれば、小魚に食ベられるのが落ちだ。 仕事や家庭と言えば都合がいい。それらを楯にして、日常に泥んこのように浸かり、常識という幅の中であくせくする。それはそれで幸せだ。 与えられた場所で、与えられた手段で、身の丈をいっぱいに伸ばしていけばいい。 この場所から、遠くを眺めるのも決して悪くはないのだ。 たくさんの遊具で遊び、満ち足りた顔が私の元へ戻ってくる。 びっしょりの水には、汗もだいぶ混じっているはずだ。 体中から水蒸気がゆっくり立ち昇り、ほどよい熱があたりへ放たれていく。 帰りの車中、「僕が思ったとおり、マクドナルド空いていたね」と息子。 「うん。たまにはこんな日もあるさ。水物だからね・・・」と私。 水物の意味がわかるのか、わからぬのか、息子はそれ以上訊かず、傘の雫や濡れた髪、衣服を気にしている。 晴れてきたら、今度こそ長い長いローラー滑り台を一緒に滑ろう。 ジェットコースターのように。 |
||
| □2003.08.20 (Wed) | ||
| ■西瓜 初物です と初夏に出された。 品のいい小皿に赤々と燃える風物 かぶりつくわけにいかず スプーンにもいっこうに馴染めないわたしは ただ美しい言葉にうっとりする。 熱しやすく冷めやすい がいのちなら 頑なに燃える仕種は また新しい。 機関銃のように胸元から種を吐き出し わたしを撃つとでもいうのだろうか。 灼熱にはまだ遠い初夏 ひとりで燃えていく風物 それが鉋屑のようにであれ 散り終えた皐月のようであれ わたしを威嚇するいのちであれば やがては甘くも哀しい物語となるのだ。 かぶりつくわけにいかず スプーンにもいっこうに馴染めないわたしは ただその美しい言葉の響きを味わう。 手のかかる食い物とのそんなかかわりもあっていいのだ。 初夏の雫のしたたり そのうえで赤々と燃える風物 初物です と言ってくれる あなたがいなくなれば わたしはかぶりつくことにする。 前へ |
||

愛知県高浜市湯山町8丁目8番地16
TEL:0566-53-7870 / FAX:0566-54-2066 / E-mail:shibata@aomi.jp
Copyright (C) 2003 AOMI Personnel-Management Office All Rights Reserved.