
 |
||
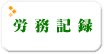 |
||
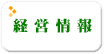 |
||
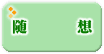 |
||
 |
||
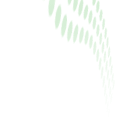 |
||

|
||||||
| □2005.09.25(San) | ||
| ■アリがたかってる 映画監督・三木聡さんが日経新聞・交遊抄に小文を寄せている。 一昔前のクリエーターの気分が横溢していて懐かしい気分になった。 かつてのクリエーターの端くれとして、こんな気分を伝えることができたら、と思う。 全文を引用させていただく。 同世代のテレビ関係者の中で、唯一「くだらないこと考える才能あるなぁ」と感じたのは遠藤達也である。最初に会ったのは24年前。当時、彼はアシスタントディレクターだったが、ディレクターの人たちより、面白いことを考えていたと思う。 1980年代の後半から90年代にかけて、私が構成作家、遠藤がディレクターというチームで数多くのしょうもない番組を作った。 深夜の時間帯は今ほど視聴率を言われることも無く、まさに「いけいけ」である。 当然、生活も滅茶苦茶、新宿や渋谷で徹夜で遊ぶ。 でも若い頃だから金はない。編集所からうちの実家に金を借りに行く道すがら「よく新聞の強盗事件の記事に遊ぶ金欲しさの犯行とか書いてあったけど、今は遊ぶ金欲しさの犯行の意味がよくわかるよな〜」とか2人で妙に納得していた。 徹夜で遊び、借りた金も消え、渋谷の宮下公園のベンチで寝ていたあの夏の日の朝。 ふと隣のベンチで寝ていた遠藤を見ると、顔にアリがたかっていた。 90年代の半ば以降、時代の大きなため息に押される様にテレビも大きく形を変え、遠藤と私が一緒に仕事をする機会も減った。会うことも少ない。 でもたまに遠藤が作った番組を見るとやっぱりくだらなくて、面白くて、少し悔しい。 |
||
| □2005.09.19(Mon) | ||
| ■ま・く・ら 噺家・柳家小三治の著書「ま・く・ら」(講談社文庫)が面白い。 その続編ともいうべき「もひとつ ま・く・ら」(同文庫)にも目を通す。 どちらも小三治の高座での“噺”を活字にしたものだが、落語よりも遥かに可笑しい。 やわらかく闇を切り裂く蛍かな あるとき小三治は、蛍の光は蛍が発しているのではなく、闇の向こうに広い光の世界があって、その薄い膜を蛍がひっかいて光が漏れてくるのではないか、と考えてこの句を詠んだ。 ところがこの句では、闇の向こうの明るい世界が読み手に届かない。 あれこれ考えた末、俳句の師匠・入船亭扇橋にご託宣を仰ぐ。 小三治の発想を生かそうと、扇橋は次のように詠む。 蛍ひとつ闇の深さを忘れゐし しかし、これでは原句が失われてしまう。 原句を残す形で、蛍にとって“切り裂く”という言葉は強すぎるという理由から、“切り裂く”の部分を“切り行く”とだけ直した。 やわらかく闇を切り行く蛍かな しかし、小三治の“闇の向こうの明るい世界”という当初の悩みは消えない。 指導を受けている宗匠・鷹羽狩行さんに相談に行くと、こう直して下さった。 やわらかき闇を切り行く蛍かな 「でもね、考えてみると、少しはあたしのことも考えてくれってんです(笑)。 いいですか?“やわらかく”という場合には、“切る”にかかるのです。やわらかく切るのです。 “やわらかき”というときには“闇”にかかるのです。 つまり、闇がやわらかいという表現は、一生あたしにはできない表現なんです(笑)。 早い話が、あたしの句は原型をとどめぬほどに、みんなでよってたかってズタズタにされてしまった(笑)」 高座での小三治のボヤキがすぐそこに聞こえてくるようで、何とも可笑しい。 |
||
| □2005.09.11(San) | ||
| ■川柳七句 惚れた目で遠く見ているちぎれ雲 人通り恥ずかしそうな風がいる そよ風が木枯らしとなる冬の駅 風騒ぐなんであんたに惚れたんか 体内の信号よそに飲む二合 風立ちぬ終章飾るいのちの樹 惚れやすく頬をつたった涙雨 |
||
| □2005.09.04(San) | ||
| ■林家正蔵 東京・台東区の雷門(浅草寺)近くにある江戸時代から続くそばの名店「尾張屋」。 かつては作家の永井荷風が通う店として有名だった。 毎日、きっかり正午5分前になると入ってきて、同じ席に座り、何も注文しないのに出てくる“かしわ南蛮”をきれいにつゆまで平らげて帰った。 荷風は、この尾張屋で倒れ、10日後に亡くなった。 尾張屋では、大きな車エビが丼からはみだす天丼が名物だ。 そばはあまり他と差が出ないから、客が腰を抜かすものを、と考案されたという。 この天丼に押され、落語家への道を歩んだ人がいる。 九代目林家正蔵。落語通でない方には、“林家こぶ平”の方が通りがいいだろう。 幼かった正蔵は、祖母に連れられてよく尾張屋の暖簾をくぐった。 いつも「お父さんみたいな立派な噺家になるんだよ。天丼ごちそうするからね」と言い聞かされて、「うんうん」言いながら天丼を頬張った。 中学3年のとき、正蔵は、父・三平に入門を願い出る。 2回追い返され、3度目にようやく許しが出た。 祖母はそれを見届けるように3年後鬼籍に入る。 師匠となった父が、ことのほか強調したのが次の言葉だった。 「うまい下手は二の次。明るく元気に一生懸命やることが人の心をうつ」 林家正蔵と聞くと、晩年に“彦六”となった先代を思い出す。 怪談話に磨きをかけた、震える声の正蔵が懐かしい。 こぶ平改め正蔵。正蔵の名が板につく日は近いか遠いか。 天丼を頬張りながら、コツコツやっていけばいい! |
||
| □2005.08.28(San) | ||
| ■似合いの夏 夏は海がよく似合う。 昨日は高浜川の最下流で漕艇競技・レガッタが行われた。 衣浦湾の東、5百メートルの橋下からスタートして、それぞれのボートが湾までの速さを競い合う。4人の漕手と1人の舵手がともに手を取り合い、軽やかなリズムを作り出していく。 結果は、出場した2組とも予定通りの予選落ち。 競技前にはや祝杯をあげている40過ぎの元若者では、勝つどころか、準決勝に残るのを良しとしない心意気が効を奏して、他チームに大差を付けられての惨敗。 敗軍はそのまま海を後にして、レッツ銭湯へと向かった。 夏はビールがよく似合う。 夜明けからの空を覆う雲が切れて、競技中は強い日差しがくまなく体中を照りつける。 バンダナや手拭いでは覆い隠せないギラギラが、容赦なくカラダを焼いていく。 それがビールのうまさに繋がるのだから、いつの時にも海路の日和は来るものである。 惨敗の兵は、湯で汗を流してから、銭湯内のレストランで乾杯。 リラックス気分が横溢して、口元にビールの泡を付けたいくつもの笑顔が光って見えた。 そして、夏は感想文がよく似合う? 『金色のやどかり』は、あゆみという少女とやどかりのティックの物語。 |
||
| □2005.08.21(San) | ||
| ■鬼みち散策 昨日、地元高浜市で、“鬼みちまつり”が開催された。 かわら美術館隣の森前公園では、さまざまなイベントが行われた。 “鬼みちまつり”は、鬼みちウォーキングにチャラポコ踊り、昔懐かしい縁日など、個性豊かな高浜の伝統文化の灯火を絶やさぬように未来へ伝えていこうという思いが込められている。 高浜市は、言わずと知れた(?)鬼瓦の産地で、鬼のみちには、鬼瓦で形作られたさまざまなモニュメントやオブジェが飾られ、高浜市の歴史文化を垣間見ることができる。 静かな町並みの中に芳醇な歴史が息づいていて、風に頬をなでられたりすると、ハッと過去が甦ったりする。 鬼みち案内人に導かれて、鬼のみちを歩いた。 案内人の言葉にうなずきながら見る景色は、普段と違って見えた。 社寺の瓦屋根に乗せられた鬼瓦のいわれを聞くにつれ、その当時の職人の鬼瓦づくりに賭ける情熱が知られた。 一朝一夕ではものにならない“技”が、晩夏の風に吹かれていた。 |
||
| □2005.08.14(San) | ||
| ■川柳七句 週一をのんびり過ごす糸電話 晩成を信じていまだ平社員 履歴書の余白に友の名を書いた 友といる風はいのちを失わず この薔薇が好きで勤続二十年 葡萄棚見上げる髪の乾くまで 単身赴任この地も同じ雨の音 |
||
| □2005.08.08(Man) | ||
| ■三年坂 夏の家族旅行だ。 何年ぶりかの京都は、少しも変わっていないように思われた。 もっとも、神社、仏閣がたびたび変わってしまっては、文化遺産として成り立たないから、旅人のそんな感覚は古都には相応しいのかもしれない。 初日は嵐山、嵯峨野。次の日は、哲学の道をしばらく歩いてから銀閣寺、それから清水寺に寄り、ラストは三十三間堂。天竜寺から続く嵯峨野の竹林の幻想的な趣が印象に残っている。 風が竹林を抜けるたび、竹は上半ばが大きく揺れ、葉が次から次へこぼれ落ちる。 そんな嵯峨野の“妖しさ”が、古都に奥行きを持たせているのかもしれない。 哲学の道は、子供たちとはしゃいで歩いた。 炎天に堀も水枯れしているのか、わずかな水が底を這うように流れている。 恋人たちの語らう道に人影はなく、百日紅だけが律儀に咲いている。 哲学の道で疑問が深くなる 北尾龍瑞 清水寺へなだらかな坂を上がっていく。 伊集院静の小説に「三年坂」というのがある。 三年坂は、清水寺の本流・清水坂の支流とも言うべき石畳の坂で、さらにその支流に二年坂がある。伊集院の小説は次のような鮮やかな描写で終わる。 坂道を下りながら、宮本は竹細工屋の老人が話した母とあの男の様子を思い返した。 何か長い時間をかけて、母に騙されていたような気がした。 何から何まで息子のために生きているふうな顔をして世間を早脚で歩きながら、ちゃんとあの 銀鼠の帯の奥に母は愛らしい一人の女を隠していたのだと・・・・・・。 カサカサと蝉籠を揺らすと夏の日の日傘を差してバスを待っていた母の姿がよぎった。 思い出す度にせつなくしか映らなかった母の顔が、かすかに微笑んでいた。 「馬鹿だね、甚。女房一人うまく仕切れないのかい」 という顔をしていた。 そうかも知れないな。すると、和江の顔が浮かんだ。 宮本は少し急ぎ脚になろうとして、身体を傾けた。 三年坂の石畳にパラパラと雫が走った。 見上げると雲間に陽は差して、天気雨である。 京都は何とも情緒のある町である。 |
||
| □2005.07.30(Sat) | ||
| ■ハーモニカ 回覧板に、やさしいハーモニカ(入門)講座のご案内、とあった。 主催は高浜市文化協会。最近、高浜市文協も粋な講座を企画する。 一昨年か昨年か、高浜文協のアンケートで、希望する講座名に、“ハーモニカ”と“落語”と書いて提出した。その一方を取り入れてくれたのかもしれない。 早速申し込んだ。初回(8月8日)が今から待ち遠しい。 ハーモニカとの出会いは、小学校時分に遡る。 あの頃の低学年の音楽の授業には、ハーモニカがツキモノだった。 やさしい音色で奏でる「故郷の人々」や「草競馬」、「新世界」が懐かしい。 僕らの何世代後からハーモニカの授業が消えてしまったのだろうか? そして、それはどんな理由からだったのか? そんなことを見つめたい気もするが、自分の価値観を前面に出せば、それは「つまずきの石」を増やすだけで、人知れず他人を縛ってしまうのだろう。 まあ、ハーモニカのやさしい音色が帰ってくることだし、うまくなれるよう精進しよう。 あの頃の夢を吹いてるハーモニカ 比呂志 申し込みが少なくボツにならなけりゃいいが! |
||
| □2005.07.23(Sat) | ||
| ■あてのない旅2 土曜日は少しゆったりできる日だ。 朝寝をしても叱られないから、いつまでも寝床の中にいる。 起きたり、眠ったり、起きたり、そしていつの間にかまたウトウトしている。 昨夜といっても暦の上では今日なのだが、床に就いたのが3時頃。 それまで何していたのかって。 酒飲んで、伊集院静の小説読んで、柳家小三治の新刊書「バイク」に目を通す。 それからお決まりの落語。志ん朝の「宿屋の富」を聞いていた。 だからまぁ、今日はあてのない日にしてしまおう。 たまには、ウトウトしながら、夢の中でトキメキたいよね! 昼頃に起きて、カップヌードルを食べて一息つく。 すぐに敷地内の雑草を抜くよう言いつけられる。 それから、息子がJAで借りている芋畑の雑草を引きに行く。 収穫までの間、何度も草取りにかり出されるだろう。 運動不足の身には、それもいい。 汗をかいた分だけの爽快さをしばし味わうが、それも麦の酒ですぐに補充してしまうから、我が身はつかのまの休息に浸ってはいられないだろう。 夕方には子供とキャッチボール。三男坊が少しずつ腕を上げている。 サイドから投げる速球はグラブの音を響かせる。 鉛筆を握る仕事の身には少し堪えるが、ときおり流れる涼風が心地いい。 あちこちにノウゼンカズラの花が咲いている。 オレンジ色の花々は、沈んでいく太陽を想わせるが、今日は一日中曇りだった。 曇りの日のあてのない旅・・・か。 明日は朝からボート漕ぎが待っている。 |
||
| □2005.07.16(Sat) | ||
| ■あてのない旅 きりんそう(ベンケイソウ科)が紙上に咲いている。 海岸の岩場だろうか。岩と岩との間から周辺一帯が黄色く染まるほど群生している。 掌サイズの葉の上に鎮座して咲く様は、タンポポのようにかわいらしく、花は細かな小菊を一杯つけたようで、海風に負けまいと賑やかなのがいい。 あきのきりんそうの名は良く聞くが、文字通りきりんそうは、あきのきりんそうの本家本元なのであって、人の目に留まらないところでひっそりと咲くのを身上としているのだろうか? 写真家・木原浩さんが「あてのない旅」を語っている。 「あてもないといっても、花を探しての旅である。 嗅覚が働いて、緑が豊かで深く、植物相に変化がある場所には自然に足が向く。 そういう場所はなぜかあまり人が来ないので、居心地がいい。 気が散らずに撮影にも集中できる。 そうして気に入ると、それ以降何度か同じ場所へ足を運ぶことになる」 「新潟から青森にかけての日本海側の海岸線も、気に入っているロケ地のひとつだ。 夕方撮影を終えると海辺へ出、車の中か砂浜にテントを張って一晩を過ごす。 時には投げ釣りなどして、キスやハゼなどの小魚を調達し、夕陽が沈むのを眺めながら一杯やる」 夕陽が沈むのを眺めながらの“一杯”。至福のときだろう。 未遂に終わったが、かつて、スケッチ旅行を企画したことがある。 おむすびかサンドウィッチをお弁当に、散歩がてらに1日ぶらぶら・・・。 スケッチブックと鉛筆と絵具、水筒に水を入れて、四季折々の自然と楽しいおしゃべり。 旅先での開放感から思う存分スケッチが楽しめるのではないだろうか? そんなことを予感させる紙上のきりんそうである。 |
||
| □2005.07.09(Sat) | ||
| ■川柳七句 力学を学んでからの逆上がり ルネサンス三文文士の夢が降る 跳躍の選手でも越えられぬ溝 炎天にキャッチボールの雲が湧く 後逸のボールをかくす花ざかり グローブを買えぬ子どもがうまくなり 走塁に風の匂いをかいでいる |
||
| □2005.07.02(Sat) | ||
| ■ビワの実 隣家のビワの実が、いつのまにかなくなった。 毎日眺めている身にとって、ビワの実がなくなることは、わが身をなくしたようで少し辛い。 眺めているからといって、所有しているわけではないので、隣人が収穫して食べてしまうことに何ら不思議はないが、ここらがモノの錯覚というやつで、いつしか眺めているうちに自分の所有物となってしまったのである。 物ならばまだいい。これが女性、とりわけ人の持ち物であったならどうであろうか? イカシテイル婦人を眺めているうちに、自分の所有物になってしまったら・・・・・・。 無論、錯覚のなせるワザで、心にしまい込んでいくうちに、この婦人はいつしか愛人へと変貌を遂げていくから、他所の人と腕組んでいたりすれば、心の拠り所を失くして失望するか、嫉妬の炎がめらめらと燃えていくのかもしれない。 執着するのが良くないのだろう? 軽く水で手を洗うように、さらっと流していくことが何事も大切なのだろう。 それにしても、ビワの実はうまかっただろうな。 冷蔵庫で冷やして、薄皮を剥いで口に放り込めば、冷たい甘味が口一杯に広がり・・・・・。 執着は死ななきゃ直らないという。 それゆえ、まだ生きていける。 ビワの実を見ているだけの昨日今日 比呂志 |
||
| □2005.06.26 (San) | ||
| ■ボールの行方 夏至が過ぎた。暑さはこれからだが、日はしだいに短くなっていく。 子供たちと公園でキャッチボールをし、落球したり逸れたボールを追っていく。 ひとまとまりの緑がボールを隠し、緑を掻き分けて捜す手の甲や腕からも汗が流れる。 これからはしばらく川遊びがいい。 涼風が揺らす川面に顔をつけて手長海老を探すのを日課にする老人。 手長海老を天麩羅にして、酒と親しむ日常がひどく新鮮に見える。 季節は、ボールもバットも過去へ流していく。 小さな緑のこむらは、はにかむように風に呼応する。 ボールの行方はやがて風が教えてくれるだろう。 天麩羅を肴に縁台でビールを飲る老人。 風が風と触れ合い、いつの日かこの老人のように、わたしも川面に顔をつけるだろうか。 夕暮れて、縁台の前を通り過ぎる子供たち。 そのグローブの中には失われたボールがさも大事そうに仕舞われている。 |
||
| □2005.06.19 (San) | ||
| ■柳家小さん 夏目漱石の「三四郎」の中に柳家小さんが登場する。 名人と言われた「三代目小さん」である。 寄席にいつも出ていて、漱石に言わせれば、全くもって“もったいない”ということだった。 柳家三語楼が来秋に「六代目柳家小さん」を襲名する。 落語通にはご案内の通りだが、五代目小さんは、人間国宝の落語家だった。 弟子たちが、人間国宝・小さんを桐の箱に入れて衣に包んで・・・・・・というシャレが可笑しくもあり、悲しくもあったのを思い出す。 人間国宝よりも、永谷園のおじさんの方が遥かに似合っていた落語家だった。 その息子、三語楼が六代目を継ぐ。寄席で三語楼の落語は良く聞いていた。 あの頃の三語楼は、お世辞にもうまい落語家とは言えなかったが、小さんの息子という方々の雑音に屈することなく、大ネタを掛けていく意欲は買われた。 20年という歳月が三語楼を大きくしていったのだろう。 三語楼がどんなふうに化けていったのか、あるいは化けていくのか、しかと確かめたいが、“念ずれば花開く”、光り輝く六代目になって欲しい。 そして甥である柳家花緑がいずれ七代目を継ぐはずだ。 |
||
| □2005.06.11 (Sat) | ||
| ■川柳七句 六月の背骨も癖も父に似て 千年を濡らした雨が今日も降る 書きかけの万年筆の手記滲む 生きている証で越える水たまり 六月の雨は詩集の中に降る 書斎からインクが匂い外は雨 哀しみを昨日へ流す雨よ降れ |
||
| □2005.06.05 (San) | ||
| ■遍路の旅 お遍路さんといえば、普通は四国八十八箇所を巡り歩く巡礼を指す。 しかし、この国にはいろいろな“四国”があって、例えば、この愛知県でも三河新四国とか知多新四国があり、巡礼の旅人は霊場に、溜まり溜まった垢を落としていく。 人が生きるということは、無垢の体に垢を溜めるようなもので、やがて溜まった垢を落とそうと巡礼の旅に出ていくのだろうか? 亡き父が死ぬ半年前に、元気になったらお遍路さんの旅に出たいと言っていたことを思い出す。 それを目標に生きていたのかも知れない。 もう叶わぬ願いだが、人はそんな思いに駆られることが人生の節々にあるのだと思う。 新緑がうれしいですか 父が逝く 新緑の頃、父はうれしそうな顔で窓を覗き込んでいた。 病室から見える青若葉が、生き生きとしていて羨ましかったのかも知れない。 年を取れば誰だって若い子が羨ましい。それが正直な気持ちだ。 青葉若葉に、自分の行く末を託していたのではなかったか。 病室に一縷の望みを刺繍する そんな期待も今となっては虚しいが、生きるとはそういうものかも知れない。 多くの思いが千羽鶴のように繋がって、いのちは満たされていくかのように見えるが、やはりいのちは、虚空に浮かぶ青い月のように、どこまでも移ろいやすいものなのだろう。 それが分かっていればいいのかも知れない。 平成17年6月3日、午後6時3分、父が逝った。わかり易い数字を残して。 |
||
| □2005.05.29 (San) | ||
| ■石榴の花 初夏を彩るように石榴の花が咲いている。 朱色の花は、何気ない素振りでいても人の目に留まる。 水仙を逆さにしたような花房は少女のようでもあるし、淑女のようでもある。 梅雨前のひととき、黄緑色の若葉と何を話しているのだろう。 少年の中の少女のように、少女の中の少年のように、そんなときめきがいくつも咲いている。 あでやかな口紅が心の淵に交差して、あの頃の汗まみれの感情が蘇える。 「君はとてもいい匂いだ」 「私は香水をつけてないわ」 「洗いたてのハンカチのようだ」(サンセット大通り) 「あなたのように美しい人なら、サハラ砂漠を歩いても、砂があとを追うでしょう」(踊る海賊) 「このままだと笑顔でさよならを言えなくなるわ」(旅愁) 「片想いでもいいの。二人分愛するから」(荒野を歩け) 「君は何を美しいと思う?樹かい?だったら君は樹に似ているよ」(パリの恋人) 「あなたのいない町へ連れてって」(気まぐれバス) 映画のワンシーンを持ち出すまでもないが、石榴の花はこうした麗しい映像を想起させる。 石榴の花の朱色は、やはり口紅の色なのだろう。 「ローマの休日」でヘップバーンが注していた紅が朱色であったらいいなと思う。 石榴の花が好きな訳だ! |
||
| □2005.05.22 (San) | ||
| ■こころのページ 日本経済新聞・夕刊で“シニア記者がつくるこころのページ”が始まった。 「こころ編集室」からのメッセージには次のように記されている。 人生や社会、文明などについて、深く考えるきっかけを提供したい。 このページのねらいです。 執筆するのは、定年を数年後に控えた東京、大阪本社の編集委員25人。 その1人、「奥の細道」を歩く土田編集委員を千住大橋で見送りました。 「おーい、大垣で祝杯上げような」 おそらく編集委員たちは、企業戦士として家庭を顧みず、仕事第一を貫いた人たちなのだろう。 そんな来し方を振り返ったとき、何かわだかまりが残ったに違いない。 誰だってこころに帰るものだ。そうして、こころに忠実な生き方を模索する。 それが例えば、“「奥の細道」を歩く”だったのだろう。 編集委員・土田芳樹さん(58歳)は、300年以上も昔の元禄2年(1689年)、松尾芭蕉が約5ヶ月かけて歩き通した「奥の細道」の同じコースを同じ時間をかけて歩こうとしている。 「列車やクルマなど乗り物が発達した時代に、徒歩の旅は最高の贅沢でもあり、歩くスピードに見合った新たな発見があるに違いない。 季節で移り変わる農山漁村の風景、商店街の変貌。 地域の人々との出会いや、古い友人との再会・・・・・・」 行春や鳥啼魚の目は泪(ゆくはるやとりなきうおのめはなみだ) 芭蕉の句を紐解いて何かが見つかるはずだ! |
||
| □2005.05.15 (San) | ||
| ■川柳七句 国電のたびたび外れる蝶つがい 新緑がうれしいですか 父が逝く 緩やかな丘陵を剥く夏ミカン 歯ブラシが真顔をぐいと歪ませる この国のかたちで煮てるイチゴジャム 名も知らぬ花だが明日に咲いている 甘酸っぱいジャムの向こうの積乱雲 |
||
| □2005.05.07 (Sat) | ||
| ■弱くたっていいじゃないか 1枚の葉書が届いた。 幡豆郡一色町味浜にある普元寺(ふがんじ)副住職・西脇顕真さんからである。 普元寺では定期的に「日曜法座」を開催していて、私はたまにお邪魔する。 この手の話は心が和むからいい。 和菓子とお煎茶をいただき、経をとなえ、話を聞く至福のときである。 さて、聴聞通信として記された、副住職の“文”がいい。 私たちの気づかない何かを教えてくれる。 『弱くたっていいじゃないか』 「人間何といっても健康が一番!病気になったら駄目です」 とテレビの人気司会者が力説していました。「健康でないといけない。病気になったら駄目だ。 強くないといけない。弱いものは駄目だ」というのは、しかし、冷たい言葉ですね。 生涯治らない病気をかかえて生きておられる人にとっては辛い言葉ですね。 生まれつき障害を持ってみえる身体の弱い人にとってはきびしい言葉ですね。 病気で若くしてこの世から去っていかれた人は軟弱で駄目な人なんでしょうか。 阿弥陀如来という仏さまは、こういう人はいいが、ああいう人は駄目というように私たちのいのちを優劣でご覧になりません。私たち1人1人を他人事のように批評するのではなく、自分のこととして大悲してくださる仏さまです。 いかなる人も排除することなく例外なしに摂めとって捨てないと誓われた仏さまです。 健康な人も病気の人も強い人も弱い人も、そのいのちそのままで「あなたは大切な人だ。かけがえのない如来の子だ」と認めてくださいます。 病気になったら神仏にすがってでも治してもらいたいというのが人情ですが、治るとは限りません。そうではなくて、たとえ病気になっても健康であっても恵まれたいのちが続く限り、ありのままの自分を大切にして生き抜いていく道を開いていただくことが仏の教えに遭うということでしょう。その道は死という虚しい滅びに向かう道ではなく、お浄土という光に満ち満ちたさとりの世界へ続く道です。弱くても強くてもいのち一杯に歩ませていただける、たのもしく安らかな道なのです。この道を、ご一緒に歩んで往きませんか。 |
||
| □2005.05.01 (San) | ||
| ■雨の物語 久しぶりの雨である。大粒の雨だれが窓ガラスをたたく。 夕方から降りだした雨が、しだいに強さを増していくのは、何かを語っているのだろう。 筍梅雨とはよく言ったもので、竹の秋を告げるのは雨でなくてはいけないのだろう。 色んな場所で世話人を引き受けているせいで、原稿を頼まれることがある。 他愛のない日常を書くのとは違って、論文の類は苦手である。 起承転結の中の、起が起のままで終わってしまうことが再三再四である。 どこまでいっても話が広がらない。といって、ディテールが巧みかというとそうでもなく、要は内容がないだけの話と片付けられる。 欅の新緑が見事に整ってきた。この雨で木も葉もよけいに微笑むだろう。 水晶のような滴が地球を潤し、地球は大地の上の生き物をゆっくり生成させていく。 朝になればすっかり変わったいのちがあるだろう。 夜仕事で、文が書けない日が多くなった。仕事を含めた日常の疲れがそうさせるのだろう。 それに引きかえ、朝はすんなり言葉が放たれる。 雀のようにかしましくはないが、言葉がゆっくり羽を広げていく。 金盥の光が目を射すように、文が力を持って余白に投げ入れられる。 どこまでいっても朝の力強さに変わりはない。 5月。木々も草花も、一番いい季節を知っているのか、一斉に葉をつけ、花を咲かせていく。 雨に濡れた大地が薄緑色に匂い、朝のいのちが陽炎のように揺らめく。 うるわしい季節の花々が、時代の扉を開けていく。 |
||
| 次へ 前へ | ||

愛知県高浜市湯山町8丁目8番地16
TEL:0566-53-7870 / FAX:0566-54-2066 / E-mail:shibata@aomi.jp
Copyright (C) 2003 AOMI Personnel-Management Office All Rights Reserved.