
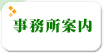 |
||
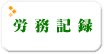 |
||
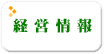 |
||
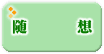 |
||
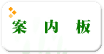 |
||
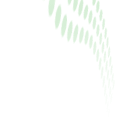 |
||

|
||||||
| □2007.12.31(Mon) | ||||||||||||||||||||
| ■蝶の翅 先週は、碧南市の冬の風物詩・「きらきらウォーク」に参加。自分のペースで、勝手気ままに歩くだけのこのイベントは、クリスマス前夜ということもあって、蝶が翅を開くように気持ちがひらく。 毎年末、碧南市の至るところでキラキラとまばゆい光を放つイルミネーション。寒さも忘れる美しいイルミネーションの下、少し幻想的な気持ちで歩けるのがありがたい。 夜店がいたるところに点在し、また和太鼓の演奏といった催しも行なわれる。家族でよし、友人でよし、恋人ならなおよし・・・いつもと違った時間と空間が広がるのがいい。 冬の祭りを初めて楽しんだ我が家の子どもたちは、その後、何となくウキウキしだした。そのエネルギーが、毎夕の耐寒かけ足に繋がっていった。 隣の高浜中学校の周りを、ただ走るだけのものだが、日頃の運動不足から大人はペースが一向に上がらない。子どもたちはといえば、どんどん前に足を進め、やがて見えなくなる。 おかげで、下半身が少し鍛えられているようだ。この調子で走れば、冬はいともた易く乗り越えられるだろう。そんなことを思いながら、晩酌にも精を出している。 そして、酔いながら、蝶が翅を広げるように明日を夢見ている・・・・・・。 |
||||||||||||||||||||
| □2007.12.23(San) | ||||||||||||||||||||
| ■偽りの季節 南天の実の赤々と娘が嫁ぎ 荻原柳絮 冬至が過ぎ、明日はクリスマス・イブ。年末は何かとせわしないが、新しい年が来るというので何とかやっていける。初冬の町のいたるところに、今年も南天が実をつけた。 昨今は偽りの季節とか。“偽”が今年を象徴する字というから、世の中は間違った方向へ進んでいるのだろう。その中で、赤い実を次々に結ぶ南天は、えらいものだ。 つい先日、我が家にも偽装があった。バスケットボール部に入部した中学1年の次男坊が、夏休み明けから、練習に顔を出していないことが、今月初旬の三者懇談会で発覚したのだ。 毎朝、同じ時間に家を出て、3ヶ月間もどこで何をしていたのか?体育館横で宿題をしていたというが、サボっていることを親にも言えず、本人も辛かったのだろうナ。 母親はショックで寝込みそうになったほどで、その気持ちはよく分かるが、そんなことで寝込んでいたらこの先、何度寝込むことになるか。親子の関係なんてそんなものだろう。 子は親に心配をかけるものだ、ということが分ればいいのだ。しかし、これが幸いしてか、ここ1週間、父親が、次男坊に勉強を教えることになった。 父親に教えられるのを嫌っていた少年が、自分の不始末を反省(?)して、父のもとへ通うのもいいことだ。いつまで続くか分らないが、そんな日があったと、後で振り返ることもあるだろう。 「南天の実の赤々と娘が嫁ぎ」。次男坊は男だから嫁ぐことはないが、しかしこの句の情意が父親の心の襞にまだ突き刺さっている・・・。  光に染められた南天の葉 |
||||||||||||||||||||
| □2007.12.09(San) | ||||||||||||||||||||
| ■川柳七句 裏切りになれたレモンの丸齧り 水を切る小石 等身大の僕 泣き納め笑い納めの味噌おでん 皮膚からの実しやかな予告編 巡礼に抒情の地図が開かれる 防波堤のこちらで探す句読点 不揃いの毛糸で明日を温める |
||||||||||||||||||||
| □2007.11.25(San) | ||||||||||||||||||||
| ■大豆の収穫 正座して米寿の母が豆たたく 加藤ノブ子 今日の中日俳壇(中日サンデー版)で見つけた俳句。「豆たたく」は、大豆を収穫したことのある人にだけ分かる表現ではないでしょうか?選者の粟田やすしさんが、こんな評をしています。 森田峠に<日向へと飛び散る豆を叩きけり>がある。日当たりの良い庭に筵を敷いて乾燥さ せた大豆を棒で叩いて莢から実をとるのである。<正座して>が確かな写生。 この句が実感できるということは、何を隠そう、一昨日、昨日と大豆を収穫したのです。農家の方に借りた畑に、初夏、豆をまき、初秋は枝豆を少し千切り、そして晩秋に実を収穫。 一度まけば、放っておいても大豆は実を結んでくれます。何と手軽な野菜なのでしょう。そして、収穫。実をたわわにつけた大豆の茎を根から引っこ抜き、束ねて、棒で何度も叩きます。 叩くと鈴の音が鳴り、バラバラと実が落ちます。中には日向へと飛び散るのも。妻と三男と三人で手分けして収穫は終わりますが、本当はここからが大変、大豆と他を選り分ける作業です。 この作業を妻に任せ、男はそれぞれの持ち場へ行ってしまいます。そして夕方、選り分けられたきれいな大豆をビニール袋の中に手を入れて握り締めます。何という安堵感でしょう。 この大豆もやがて妻の手にかかり、味噌になっていきます。熟成される静かで美しい時間が流れていきます・・・。 |
||||||||||||||||||||
| □2007.11.18(San) | ||||||||||||||||||||
| ■川柳大会惨敗! 川柳を習い始めて、4年という歳月が流れている。毎月の句会は、出席はともかくとして、毎回句を提出して、講師から添削をいただいている。 “これは”という句もあれば、“これじゃ”という句もあって、自信作が木っ端微塵に壊されることもあれば、自信のない句が、思いがけず賞賛されるときもある。 選句眼のなさに悩みは尽きないが、技量を高めようと柳友と他流試合に出向くこともあって、努力だけは惜しむまいと、ひそかに心に決めている。 今日は「岡崎市芸術祭参加 秋の市民川柳大会」(岡崎川柳研究社主催)。100名を超す参加者とともに腕を競い合ったが、どうやら惨敗。行きの威勢の良さは、帰りには“しょんぼり”。 まだまだ将来のある身には、捲土重来を期して、次に繋げていかなければならない。 落花落日 窓の心が哀しいね (兼題「窓」) 落丁も反乱となるポケット本 (兼題「ポケット」) 「店頭に情念がならぶ 姫リンゴ」(兼題「店」)などは、我ながら傑作と思っていたが、見る人が見れば、タダの句なのだろう。 |
||||||||||||||||||||
| □2007.11.10(Sat) | ||||||||||||||||||||
| ■川柳七句 倦怠が寄り添う冬の花火から 明日を見るために初心にかえる翅 未熟さを残したままの花の冷え 雨の日の遠い花野を視野に持つ 未来図が切取り線で繋がれる けしずみの香り母校はいつも掌に 路地裏の人間に舞う紙ふぶき |
||||||||||||||||||||
| □2007.10.28(San) | ||||||||||||||||||||
| ■大雨の水行? 女子プロゴルファー・古閑美保が安定した力を見せている。先週(マスターズGCレディース) は優勝。そして今週(樋口久子IDC大塚家具レディース)は昨日まで2打差のトップを走っている。 「コガミホ運動中、残業中」のアミノサプリ(キリンビバレッジ)のCMで、今や全国区になった古閑さんだが、マスコミの中で浮かれていると足をさらわれるのが勝負の世界。 このまま逃げ切れるかというと、“そうは問屋が卸さない”のが常で、欲に走ると、入るパットまで入らなくなるものだ。何事も“平常心”を保つのは、至難の業なのだ。 今日の新聞のスポーツ面を開くと、「古閑の好調維持験担ぎいらず?」と小見出し。興味津々で読み進めていくと、子を思う親のありがたさで、涙が零れそうになった。 前週1年ぶりの好機に、古閑さんの父親の宏二郎さんは大会2日目の夜、自宅で験担ぎのため頭から冷水を100回かける水行をしたのだった。 これを記者に話した古閑さんは続けて、「今日は大雨で私が100回水行をやったようなもの。もう父はする必要がない」と笑わせた。今日も勝てればいいが・・・。 結果は残念ながら1打差の2位。まぁいいさ、僅差で負けることも勉強だ。それを知っているのは、古閑美保本人だろう! 古閑美保 公式サイト http://sports.nifty.com/miho34/index.jsp |
||||||||||||||||||||
| □2007.10.13(Sat) | ||||||||||||||||||||
| ■川柳七句 人間の貌をいびつにする迷路 解毒剤 呑むと魂まで抜ける 家出する心が明日を描いている 落丁を見つけた指に試される 常識の檻で飼われている孔雀 非常口で戦さの爪を研いでいる 縁起木でなくても匂う金木犀 |
||||||||||||||||||||
| □2007.10.07(San) | ||||||||||||||||||||
| ■小三治的極める! 今朝の日経新聞・「詩歌・教養」欄に、しかめっ面で角刈り、ほとんど頑固という顔が写し出されている。俳句を少々やる人だから、詩歌・教養でもかまわないが、言うことがいちいち小難しい。 「落語は笑わせるものじゃない。笑ってしまうものなんです。それは師匠・小さんの遺訓であり、代々の小さんの遺訓。だから私は、客を笑わせることは恥ずかしいことだと思っています」 笑わせるものだろうが、笑ってしまうものだろうが、どちらでもいいじゃないか、という気がするが、この人の感性は、落語に限らず並外れて鋭敏だ。 柳家小三治。昔から哲学的な思索ができる人だと思っていたが、トボケた味の奥底で、妙に生真面目で凛々しい顔を見せる。繊細なんだ。繊細が服を着ているような人なのだ。 「(かつて志ん朝が、“お父ちゃん、落語ってどうやったら面白くできるの”と聞いた時)あんなにメチャクチャ面白いといわれた志ん生が言ったのは、“面白くやろうとしないことだよ”って」 「(前座噺の“道灌”を今でもたびたび演ずるのは)基本に返るということ。当時、小さんのを聞くと、何でこんなに面白いんだろうと思う。いろいろやってみるが、しょせん比べものにならない」 「いつか自分も“道灌”でお客さんに喜んでもらえる噺家になりたいと思った。だから,その時の気持ちに帰るんだ。そして今やっと“道灌”を面白くしようとしなくなった」 半世紀の春秋の中で、小三治は噺を面白くしないで、客がくすっと笑う術を学んだのだ。その道のりは細く、長く、険しいものだったに違いない。昨今の落語ブームについて小三治は・・・。 「アブクは必ずはじける。その後はアブクの下にある普通の水が出てくる。元に戻るわけです。別に言うことはありません。みんな好きなことを精一杯やればいいんです」 |
||||||||||||||||||||
| □2007.09.30(San) | ||||||||||||||||||||
| ■佐久島散策 紺碧の島・佐久島散策コース 8.2km 2時間半 佐久島歩け歩け海原三里 今日は、長男坊をお供に小雨が霧状に降りしきる中、時に傘を差しての佐久島散策。地図左端の佐久島西港を皮切りに、外浦古墳、ソテツの広場、日だまりの広場と、地図を時計回りに。 そして、八剣神社から筒島にある弁財天へは地図右側を南下。筒島は地図では孤島のように見えるが、防波堤で続いている。弁財天の後ろにはみごとな竹林が雨に濡れていた。 続いて大島。防波堤を歩くこと数分、佐久島海釣りセンターにはいくらかの人出。何が釣れるのか、釣り人を尻目に、2004年に完成されたという佐久島アート「佐久島のお庭」をしばし体験。 「波の音を聴き、潮風に吹かれながらアートを満喫」がうたい文句だが、この雨の中、悠長にもしていられず、皿のモザイクでできた小道を一通り歩いてすぐに退散。 まだいくらか残っているデイゴの真っ赤な花が、少し南国を思わせた。ラストコースは大浦海水浴場まで。ゴールと書かれた幟がさびしそうに小雨に濡れていた。 大浦海水浴場で昼食。大粒のアサリがいっぱいの味噌汁をいただき、朝コンビニで買ったサンドイッチ、おにぎりとともに冷えた体内に流し込んだ。 午後からは、「歩け歩け」から離れて単独行動。といっても長男坊がお供ではいささか不自由さが残るが、「三河湾の黒真珠」といわれる佐久島の迷路のような路地を彷徨う。 「大葉邸」は、その路地集落にある築100年の古民家をアートとして作品化したもの。アーティスト・平田五郎さんの「佐久島空家計画」は見事なもので、静かな時間が流れていた。 次は、石垣(しがけ)海岸にある「おひるねハウス」。大葉邸のツイデに寄ったのだが、これが中々いい。波の音を聴きながらうたた寝できるスポットで、最高の贅沢ではないか? 帰り際、「弁天サロン」、「となりのおみせ」に立ち寄り、およそ4時間に及ぶ散策が終了。それにしても肌寒い日だった。海が青いということは幸せなことなのだ! 癒しとアートの島 ようこそ佐久島へ http://www.japan-net.ne.jp/~benten/  佐久島絵図 |
||||||||||||||||||||
| □2007.09.23(San) | ||||||||||||||||||||
| ■最後の運動会 昨日は、三男坊の小学校での最後の運動会。残暑厳しい中、児童もがんばったが、父兄もよくがんばった。ギラギラの太陽に身を晒し、真夏の犬のようにハァハァ肩で息をした。 それで、木陰に腰を下ろし、冷茶を飲むときの至福は何物にも変えがたい。“生きた心地”とはよく言ったもので、喉仏のあたりの“いのち”の粒が、体中のいのちを呼び起こしていった。 昼食はいつものようにおにぎり。木陰をわたる風がおにぎりを湿らせていくから、別に用意した海苔で包んで食べる。パリパリの歯ごたえが海苔のうまさを引き立てる。 午後1番の競技は、親子二人三脚。最後の運動会は父兄とて同じで、長男の入学から数えて15年目の若さを引き摺った肢体が太陽の日射しを一身に受けて、紙風船のように舞っていく。 チームが一丸となり、ときにしぼみそうになる紙風船だったが、結果は優勝。最後の運動会に相応しく、どうやら神様からのメッセージが届いたようだ。 さて、子どもにどんな言葉を贈ればいいのか?体育委員として、運動会の全種目に縁の下の力になっていた。多くの力が結集されて、一つのことが結実することが理解できただろうか? そうであれば、義務教育の大切な部分が分かったといっていい。思いやりや努力やときに犠牲などが、大勢の中で学べるのが学校なのだということも・・・。 運動場に一陣の風が抜ける。風は競技する児童や父兄の頬をやさしくなぜて、緑一杯の百葉箱の方へ流れていく。風がいのちの芽を育んでいるのだろうか? そして、紙風船のように舞っていく親子の背を押して、膨らませたり、しぼめたりするのも、また風のいのちなのだということを、子どもはやがて知ることになる。 |
||||||||||||||||||||
| □2007.09.17(Mon) | ||||||||||||||||||||
| ■桂川 京都嵐山・渡月橋の下を轟々と流れる川は、「桂川」と記憶していたが、「大堰川」と書かれている文献もあって、迷ってしまった。 本当はどちらでもいいのだが、一昨日嵐山・嵯峨野へ行ってきたことだし、調べてみようと思った。文献を斜め読みすると、どうやら地域によって呼び名が変わるようだった。 行政上の名称は桂川に統一されていますが、地域によって呼び方が異なり、上流から嵐山 付近の間では大堰川(おおいがわ)・保津川(ほづがわ)など、嵐山付近では大堰川、その 下流では桂川・梅津川(うめづがわ)と呼ばれ、親しまれています。 なるほど、そういうことか。この川の支流というか、分流には「鴨川」もあって、水の都に相応しく、京の人々が川を愛している様子がうかがわれる。 晩秋の嵐山は、いたるところに紅葉が映えて、それはそれは美しいだろう。 渡月橋から見る景色は、秋宵一刻値千金か。もう一度行きたくなった。 今はもう秋つぎ足せぬ命の火 田中 伯  嵐山・渡月橋 |
||||||||||||||||||||
| □2007.09.08(Sat) | ||||||||||||||||||||
| ■川柳七句 軽易さが炙り出された半世紀 観覧車の哀しみ少しだけわかる もう少し昭和でいたい紙芝居 緋の色がまだ底辺にうずくまる 嫁がせてからは手酌の月見酒 埋もれてる死骸が花の彩に香に 残された者にかなしい夫婦箸 |
||||||||||||||||||||
| □2007.09.02(San) | ||||||||||||||||||||
| ■大須演芸場 先週の日曜日、大須演芸場を久々にのぞいた。寄席に“鑑賞”という言葉は似合わないから、遠足でも行く気分で、“見学”。あの妖気漂う場所に、しばし身を置いた。 午後2時。薄気味悪い扉を開けると、日曜なのに客は10数人。この日は、栄や名駅前で「名古屋祭り」の真っ最中だから、そちらに客をとられたのだろうか? まぁ、それは世辞というやつで、相変わらずの入りの悪さは、昭和からの名残だ。 こちらは7人の団体だから、客足が一気に跳ね上がった格好だ。 芸人は、客が何人入ろうが興味がない様子で、十年一日の芸を平成の世にも晒している。入りの悪さだけでなく、芸にも昭和の名残があって、それがいいノスタルジアを醸し出している。 これなんだ、この寄席がまだ続いているのは。何度も潰れかけた寄席が、地平すれすれで落ちずにいるのは、こうした妖しい空間をたまらなく好きなファンがいるからなのだ。 これらファンがいるから、席亭も身銭を切りながらも、興行が止められずにいるのだ。“希少価値”というか、“侠気”というか、損得を越えた“生きがい”が、そこにはあるのだろう。 この日の演芸は、ざっと次のとおり。やっぱり妖しい・・・?
|
||||||||||||||||||||
| □2007.08.19(San) | ||||||||||||||||||||
| ■光の一句 とある郵便局の片隅。無造作に置かれているパンフ。 光るもの、光ること、光る人・・ あなたの光を句に込めて 光の一句 募集します。 なんだ、俳句の募集か。 「三重県は芭蕉さんのふるさとです」という一文が踊っているのを見ても、三重県は俳句に相当力を入れているのだろう。 さて、「光」。どんな俳句をしたためればいいのだろうか? 俳句は、思いを直截に表現していかなければいけない。その辺が「技量」というやつで、長いあいだの積み重ねがやがて生きてくる。 光るものとて仏壇があるばかり 捨てた方の道がおいしそうにひかる 母に降る雪はほのかに光りたり ある危機の予感に光る春の潮 |
||||||||||||||||||||
| □2007.08.11(Sat) | ||||||||||||||||||||
| ■川柳七句 濾過すると噂話がてんこもり 日曜の祈りコーヒーの匂いから 凡庸なおとこにできぬ尻尾切り 負けるたび妖気を少しずつ溜める ヒロシマが癒されていく大花火 みんな海に帰って行くのだ恐竜展 潮騒の町に行きたい離職票 |
||||||||||||||||||||
| □2007.08.05(San) | ||||||||||||||||||||
| ■四季のスケッチ お元気、ご多忙でお過ごしの事と存じます。「群生」52号の原稿が未着です。 八月十日(金)までに郵送か又は刈谷市社会教育センターへ届けて下さい。 貴兄のさわやかな味のあるエッセイは、「群生」に欠かせないので、無理をして下さい。 刈谷文化協会・文芸誌の締め切りが過ぎていたので、そろそろと思っていた矢先、事務局から督促状を頂いた。怒気を含んでということもあるまいが、少々字が震えている。 こうなれば、いつもの一夜漬けのヤッツケ仕事しかないが、何を書こうか? 「落語」か「川柳」か、はたまた「詩」という、毎度のパターンを繰り広げることになりそうだ。 さて、書き出しはどうしたものか。頭の中でパチッと閃くものがある。 「四季のスケッチ」という詩を思い出した。 清岡卓行さんの詩集『四季のスケッチ』を久しぶりに眺めている。 読むのではなくて、新聞のチラシをちらと眺めるように、目でページを撫でていくのである。 ともかく、『四季のスケッチ』の中の「耳を通じて」という詩に時々逢いたくなる。こんな詩だ。 心がうらぶれたときは、音楽を聞くな。 |
||||||||||||||||||||
| □2007.07.29(San) | ||||||||||||||||||||
| ■大人の祭り 朝目覚めたら、子どもたちがいない。夕べの話からすると、どうやら犬山のモンキーパークへ行ったらしい。家人が犬猿雉をお供に連れて、プチ旅行と洒落たのだろう。 子どもたちには、「暑中、お気の毒」と言いたいが、気の毒なのはむしろ猿たちで、猿も物見遊山の人間どもの相手をしなければならず、益々暑い思いをしているのではないか? もう何年になるのか、三河湾に“兎島・猿が島”が健在だったころ、夏場の猿たちは今よりずっと元気だった。生きるすべを潮風に教えてもらった海の猿だったからだろう。 そこへいくと、モンキーパークの猿たちは脆弱だ。生きるすべを他から与えられたものに、生きる資質は芽生えない。一度、猿が島で修行したらどうかと、未だ見ぬ猿に言っている。 こんな批評をするのは、朝の目覚めが悪かったせいだ。気持ちの荒みは、いつもそこら辺に素があって、眠り薬代わりの深夜映画を見たりするとテキメンだ。 ということで、朝から体も頭も一向に冴えない。参院選挙には行ったものの、思いとは別の人選をしてしまった。今日中に仕上げなければならない川柳の作句の方も、パッとしない。 「半田市制70周年はんだ山車まつり記念川柳大会」の兼題は、「祭」と「港」。いつも一夜漬けのヤッツケ仕事で、どうにもならない代物だ。一笑に付していただければ幸いだ。 父ちゃんがいると祭りの音がする 金魚鉢逆さに吊るし待つ祭り 有史以来 母の港があたたかい 港にも秋 恐竜展終わる さて、参院選の結果が待ち遠しい。与野党逆転なるか・・・。大人の“祭り”がやってきた! |
||||||||||||||||||||
| □2007.07.22(San) | ||||||||||||||||||||
| ■大人の夏休み まだ真夏という感覚には乏しいが、子どもたちの夏休みが始まった。大人たちとて何だかうれしい気分になるのは、「夏休み」という言葉のノスタルジアなのだろうか? 「夏休みと聞いて何を連想する?」こんな質問を子どもたちに投げかけてみた。大人とはずいぶん違った回答が得られるはずだし、そこからいろいろな思いを吸収できる。 海、西瓜、向日葵、風鈴、かき氷、心太・・・あのころの少年少女は、およそこんな回答を寄せたものだ。今の少年少女はというと・・・? ちなみに我が家では、こんな答え。 学校に行かなくてもすむ。 勉強をしなくてもいい。 朝早く起きなくてもいい。 クーラー、アイス、プール、暑い。 肝試し、夕涼み、水風呂、歯医者、出校日・・・。 なんだ、ちっとも変わってないじゃないか。四半世紀くらいは宇宙感覚でいえば無に等しいから、変わらないのも当然か。まぁ、少し安心した。 世間は参院選挙で慌しい。野次馬にとっては対岸の火事のようなもので、何がどうなろうとかまやしないが、大人になるとそうはいかないのが社会だ。 子どもと浮世離れなことばかり言っていられない。大人になるというのはそういうことだ。だから、巷にはストレスばかりが霧のように充満してしまう。それはすべて大人から発せられたものだ。 大人にも夏休みがあっていいのでは?南欧のようにバカンスといきたい。乾いたビーチに寝そべって、浮世のことをすべて忘れてしまう時間がおそらく日本にも必要になってくるのだろう。 そんなことを思いながら、子どもたちと打上花火や線香花火、鼠花火。 やっぱり、あのころとおなじ花火だ! |
||||||||||||||||||||
| □2007.07.14(Sat) | ||||||||||||||||||||
| ■川柳七句 天気予報 赤い鼻緒がよく当たる 背伸びする遊具の中の子どもたち ジャムの瓶 光が爪を立てている 負け組にいつもやさしい夏の雨 指切りの指の固さでほぞを噛む 進化論 ヒトはこれから何になる 残光をあつめ明日の紫蘇を揉む |
||||||||||||||||||||
| □2007.07.07(Sat) | ||||||||||||||||||||
| ■生活の匂い 朝、眠気覚ましに小冊子をめくっていたら、「お知恵拝借!」のコーナー。 テーマ毎に「あなたのお知恵を拝借します」と読者に呼びかけ、投稿を促している。 今月のテーマは「朝スッキリ目覚める方法」。読んでいくと、他愛のない“お知恵”ばかりだが、中には詩的なものもあって、二日酔いの前頭葉にも甘い匂いが立ち込めてくる。 日本人の悪い癖で、「生活」という言葉のイメージにはいつも貧性がつきまとうが、生活にはいい匂いがしなくてはだめだ。川柳はそんな匂いを拾い上げていくものなのだ。 話がそれたが、「朝スッキリ目覚める方法」。投稿者の詩的な感覚を拾ってみると、生活とは何ともいいものだと思えてくる。目覚めの悪い人は、参考にしてください! 寝る前にお風呂に入り、体がまだ温かいうちに布団に入ります。 そして自分の起きたい時間、6時なら6回枕をたたいて、「枕さん朝6時に起こしてください」とお願いして寝ます。不思議とその時間に起きられます。(滋賀県東近江市 Tさん 54歳) 寝る前の数分間、心の中で「明日の私」に手紙を書きます。 そして次の日の朝、目覚めたら、前の日の手紙を心の中で受け取ります。 私は手紙の便せんの色など細かいところまで決めています。(金沢市 匿名希望さん 35歳) パンが好きなので、夜ホームベーカリーの予約をして、翌朝起きるころに焼き上がるようにしています。部屋にパンの焼けるいい香りが漂ってきて気持ち良く起きられます。(愛知県額田郡 ファーイブさん 32歳) |
||||||||||||||||||||
| □2007.07.01(San) | ||||||||||||||||||||
| ■落語鑑賞ノート其の4 春風亭正朝師の「青菜」「宮戸川」(インプレスTVインターネット落語会)。明るさと人を逸らさない誠実さにいつも好感が持てるが、加えて、落語がとても丁寧というのを感じた。 「青菜」では大田蜀山人のふたつの狂歌を引用して、暑いもの、涼しいものを表現しながら、例の「植木屋さん、ご精が出ますな・・・」に入っていく。 西陽射す 九尺二間に ふとっちょの 背なで子が泣く メシが焦げつく 庭に水 新し畳 伊予すだれ すきやちぢみに 色白のたぼ これが蜀山人のふたつの狂歌だが、正朝師はこれを丁寧に説明しながらも、笑いをとっていく。 この辺は、延ばしたり、はしょったりを日常茶飯にしている寄席芸人の確かな技量だ。 さて、噺のスジは、植木職の男がお屋敷で仕事が終わって一服。そこへ旦那が出てきて酒、肴をごちそうになる。「植木屋さんは菜がお好きか?」「大好物で」「奥や、お持ちなさい」 奥さまが次の間へ控えていて「鞍馬から牛若丸が出でましてその名を九郎判官」「んー、それじゃ義経にしておきなさい」と二人の会話。 旦那にわけを聞くと一遍あると言った品物がないのは失礼になる。菜は食べてしまって、無いので「くろう(食らう)ほうがん」、あたしが「よしとけ」てぇのをシャレて「義経にしておきなさい」 屋敷内の隠し言葉だというのを聞いてすっかり感心した植木屋。オレもやってみようと・・・。 「鞍馬から牛若丸が出でましてその名を九郎判官義経」「んー、じゃ弁慶にしておけ」 何のことか分からない人は、ぜひご一報を! |
||||||||||||||||||||
| 次へ 前へ | ||||||||||||||||||||

愛知県高浜市湯山町8丁目8番地16
TEL:0566-53-7870 / FAX:0566-54-2066 / E-mail:shibata@aomi.jp
Copyright (C) 2003 AOMI Personnel-Management Office All Rights Reserved.